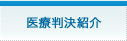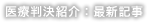東京地方裁判所平成27年1月27日判決 ウェストロージャパン
(争点)
- 担当看護師の過失の有無
- 看護部長の過失の有無
*以下、原告を◇、被告を△1及び△2と表記する。
(事案)
◇は、B(昭和3年生まれ)の子であり、 b病院勤務の内科医師である。
△2は本件病院(以下「△病院」という。)を含む全国各地で多数の病院を設置運営する独立行政法人であり、平成21年7月当時(以下、平成21年であるときはその記載を省略する。)、△1は△病院の看護部長であるとともに、医療安全管理委員会及び事故対策委員会の委員であり、これらの立場で△2の実施する「転倒・転落事故防止プロジェクト」の推進に関わっていた。C看護師は△病院のICU勤務の看護師であった。
Bは、7月23日、症候性てんかんによるけいれん重積発作のために△病院に救急搬送されて処置室で治療を受け、その後入院することになり、同月29日の事故発生後に退院するまで、ICUにある集中治療室(CCU)の個室(以下「本件個室」という。)において入院(以下「本件入院」という。)をした。当時、Bには褥瘡(仙骨部及び左大転子部の発赤)が認められたほか、糖尿病、高血圧、心不全及び変形性股関節症の既往歴や糖尿病性網膜症による視力障害(全盲)があった。また、移動はストレッチャーでする状態であった。
C看護師は、7月29日の昼食時にBの昼食の介助を担当した。介助を始めるに当たって、C看護師は、Bの病室のベッド(以下「本件ベッド」という。)の角度調整ボタンを操作して、本件ベッドの上半身方向の面を少なくとも60度程度となるように上げ(ベッドアップあるいはギャッジアップ)、Bをその上半身が起き上がる体位とした。また、本件ベッドの左右両側に2つずつあるベッド柵のうち、下半身方向左右両側のベッド柵は、下半身方向に倒すこと(柵の支柱3本がベッドの側面に沿って斜めになる。)によって、柵の高さを変更することができるようになっており、C看護師は、それらをそれぞれ半分の高さに下げて固定した上で、キャスター付き可動式のオーバーテーブル(お膳や食器を置くためのもの)を、そのテーブル面がBの身体の前に来るような形で本件ベッド上に被さるように設置した。その際、上半身方向左右両側にあるベッド柵は2つとも完全に上げた状態(柵の高さが最も高い状態)であった。
この措置をした結果、本件ベッドの両側にある上半身方向のベッド柵と下半身方向のベッド柵との間に大きなすき間(以下「本件すき間」という。)ができた。
さらに、C看護師は、Bの昼食の介助を始めるに当たり、Bの両脇をクッションで固定し、Bの体位を整えた。Bは、当時、ベッドアップ時には上半身が左右に傾いてしまう状態であり、C看護師は、Bの下半身に拘縮があり、ベッド上での身動きが不自由で、ベッドアップ時には身体が左右に傾くことを認識していた。
Bは、同日午後0時30分頃、昼食の摂取を始めた。
C看護師は、Bが食事を終えた後の同日午後0時40分頃、ICUの電話が鳴ったのを 本件個室で聞き、これに対応するため、本件個室を離れ、その際、C看護師は、本件ベッドやオーバーテーブルの状況はそのままにした。
Bは、同日午後0時45分頃、本件ベッドから転落し、本件ベッドの右側に右側臥位にな って倒れていたところ、C看護師以外の看護師によって発見された(本件事故の発見)。その際、Bは、頭部と右膝部をさすっていた。
また、Bには、本件事故直後の診察において、右頭頂部に手拳大の腫脹と点状皮下出血、 左手背部に擦過傷が認められ、さらに、頭部CT撮影、胸部、骨盤、両股関節及び両下肢のレントゲン撮影並びに胸腹部エコーが施行された結果、左脛骨遠位部が骨折していることが判明して、オルソグラスによるシーネ固定が施行された。その際、Bの診察に当たった医師は、上記固定は2週ないし4週間必要であり、その間に皮膚の障害や深部静脈血栓を発症する危険が認められ、注意が必要であると診断した(以下「本件傷害」とは、上記のような内容のものを指す)。
その後の治療については、同日中にBがストレッチャーに載せられて、自主退院したため、自宅での安静によることとされた。
Bは、12月4日に死亡し、その相続により、◇がBの権利義務を取得した。
そこで、◇は以下の甲乙二つの損害賠償請求をした。
甲事件
△1に対し、(1)本件事故がC看護師の看護上の過失に基づく不法行為によるものであり、△1が使用者に代わってC看護師の執行する事業を監督する者(以下「代理監督者」ということがある。)
に当たることを理由とする民法715条2項に基づく損害賠償請求
又は(2)△病院の看護部長として、Bが本件ベッドから転落することを防止し、また、転落した場合にBが傷害を負うこと回避する措置を採る義務を負っていたにもかかわらずこれを怠ったことを理由とする同法709条に基づく損害賠償
乙事件
△2に対し、(1)△1に甲事件の不法行為があったことを理由とする使用者責任(民法715条1項)に基づく損害賠償請求
(2)本件事故がC看護師の看護上の過失に基づく不法行為によるものであったことを理由とする使用者責任(同項)に基づく損害賠償請求
等
(損害賠償請求)
甲事件
- 患者遺族の請求額:
- 160万円
(内訳:慰謝料160万円)
乙事件
- 患者遺族の請求額:
- 10万円
(内訳:慰謝料10万円)
(裁判所の認容額)
甲事件
- 認容額:
- 0円
(請求棄却)
乙事件
- 認容額:
- 10万円
(内訳:慰謝料10万円)
(裁判所の判断)
1 担当看護師の過失の有無
この点について、裁判所は、本件事故は、本件ベッドの上半身方向の面が少なくとも60度程度となるようにベッドアップされる一方、下半身方向左右両側のベッド柵が下半身方向に倒された結果、本件ベッドの両側に本件すき間ができていたところ、ベッド上での身動きが不自由で、全盲のBが何らかの体動をし、体位を固定するために置かれたクッションが動くなどした結果、Bの上半身が大きく傾いていき、これに対してBは有効な対応をすることができず、最終的には、本件すき間のうち本件ベッドの右側のものを通じて、Bの身体が本件ベッドの右側床に転落し、その過程で本件傷害が生じたというものであると推認されると判示しました。
そして、C看護師が本件個室を離れる際、本件ベッドの高さにかかわらず、Bが体動することにより本件ベッドから転落する具体的な危険があったといえ、Bの入院の際に作成された「転倒・転落事故防止計画表」に、基本的対策として処置等終了時にはベッド柵を元の状態に戻していることを必ず確認することが掲げられていたことや、△2作成の「転倒・転落事故防止マニュアル」に本件事故と類似の事例の再発防止策として、処置中にベッド柵を使用している患者のそばを離れる場合には、短い時間であっても必ずベッド柵を上げてから離れることを徹底することが記載されていることなどに鑑みれば、転落の危険はC看護師が下半身方向のベッド柵を元の状態に戻すことによって回避可能であり、また、そうした対応を採ることは困難なことではなかったということができると判示しました。
裁判所は、C看護師が本件事故直前にBのそばから離れた際、C看護師には、半分下げていた下半身方向のベッド柵を完全に上げる方法により転落防止の対策をするべき注意義務があったのにこれを怠った過失があったものといわざるを得ず、C看護師に本件事故についてBに対する不法行為責任が成立するものと認めることができるとしました。
裁判所は、そして、△2は、C看護師の使用者であり、C看護師のこの過失による事故は△2の事業の執行につき行われたことが明らかだから, △2は、C看護師の使用者として、本件事故によってBに生じた損害につき、使用者責任に基づいて賠償する責任があるものというべきであるとしました。
2 看護部長の過失の有無
この点について、裁判所は、特段の事情の主張立証もない以上、△1とC看護師の間に、個々の具体的な看護業務一般についての直接の指揮監督関係があるものとは認め難いとしました。また、C看護師の過失の態様からすれば、原告の主張する転落防止策を△1が尽くしたとしても、本件事故の発生を防ぐことができたとまでは認め難いと判示しました。
裁判所は、△1の過失を認めることはできず、△1が本件事故について不法行為責任を負うとはいえないと判断しました。また、△1が代理監督者に該当するものとは認め難いとも判示しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。